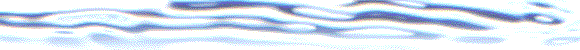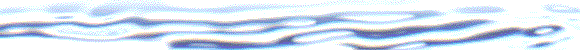
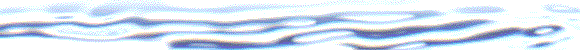
(2005年5月15日)
平成17年4月18日厚生労働省は
|
|
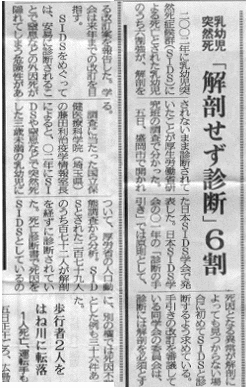 (平成17年3月6日大分合同新聞より) |
この記事は、平成17年3月6日の新聞にありました。
|
この記事から約一ヶ月後に新しい診断基準のガイドラインが出されました。 |
|
| 乳幼児突然死症候群(SIDS)に関する ガイドラインの公表について 乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドラインについて、 厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)「乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断のための ガイドライン作成およびその予防と発症率軽減に関する研究」 (主任研究者:坂上正道北里大学名誉教授)においてとりまとめを行ったので、 別添のとおり公表します。 【研究班】 主任研究者 坂上 正道 北里大学名誉教授 分担研究者 齋藤 一之 埼玉医科大学医学部法医学教授 澤口 聡子 東京女子医科大学医学部法医学教室助教授 高嶋 幸男 国際医療福祉大学大学院教授 高津 光洋 東京慈恵会医科大学医学部法医学講座教授 戸苅 創 名古屋市立大学大学院医学研究科 先天異常新生児小児医学分野教授 中山 雅弘 大阪母子総合医療センター検査科部長 仁志田 博司 東京女子医科大学母子総合医療センター新生児科教授 平林 勝政 國學院大学法学部教授 藤田 利治 国立保健医療科学院疫学部疫学情報室室長 的場 梁次 大阪大学大学院医学系研究科法医学教室教授 宮坂 勝之 国立成育医療センター手術集中治療部部長 横田 俊平 横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学教授 -------------------------------------------------------------------------------- 乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン (平成17年3月:厚生労働省研究班) 乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)は、それまで元気な乳幼児が、 主として睡眠中に突然死亡状態で発見され、原則として1歳未満の乳児に起こる。 日本での発症頻度はおおよそ出生4,000人に1人と推定され、生後2ヵ月から6ヵ月に多く、 稀には1歳以上で発症することがある。従来、リスク因子として妊婦および養育者の喫煙、 非母乳保育、うつぶせ寝などが挙げられており、 世界各国でこれらのリスクを軽減する運動が展開され大きな成果を挙げている 。原因に関しては、睡眠に随伴した覚醒反応の低下を含めた脳機能の異常、 先天性代謝異常症の存在、感染症、慢性の低酸素症の存在、 等々種々のものが考えられているが、未だ解明に至らず、 国内外の専門家によってその原因究明と予防法の確立にむけた研究がなされている。 これまで、我が国では本疾患に対する認識が浅く、解剖率が必ずしも高くないことから、 厚生省研究班(現厚生労働省研究班)は昭和57年に 「広義と狭義の定義」を作成して疾患の認識の普及に努めた。 平成8年の報告では、解剖されなかった例には「乳幼児突然死症候群(SIDS)の疑い」という定義を用いてきた。 しかし、平成7年からICD-10の採用により乳幼児突然死症候群(SIDS)が独立して統計処理されるようになって、 人口動態統計の0歳の死因順位では第3位に掲載されるようになり、 疾患の重要性が認識されるようになった。 この間、我が国では乳幼児突然死症候群(SIDS)、窒息、虐待の診断を巡る混乱が生じ、 社会的混乱を招く所となり、平成14年来の研究班では、 国際的に討議されつつある定義も参照して、 我が国における乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドラインを作成することになった。 I 乳幼児突然死症候群(SIDS)の定義: (Sudden Infant Death Syndrome: SIDS): それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、 しかも死亡状況調査および解剖検査によってもその原因が同定されない、 原則として1歳未満の児に突然の死をもたらした症候群。 II 診断に際しての留意事項: 1) 諸外国で行われている研究も考慮し、 乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断は原則として新生児期を含めて1歳未満とするが、 1歳を超える場合でも年齢以外の定義をみたす場合に限り乳幼児突然死症候群(SIDS)とする。* 2) 乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断は剖検に基づいて行い、 解剖がなされない場合および死亡状況調査が実施されない場合は、 死因の分類が不可能であり、従って、死亡診断書(死体検案書)の分類上は「12.不詳」とする。 3) 乳幼児突然死症候群(SIDS)は除外診断ではなく一つの疾患単位であり、 その診断の為には、乳幼児突然死症候群(SIDS)以外の乳幼児に突然の死をもたらす 疾患および窒息や虐待などの外因死との鑑別診断が必要である。 4) 外因死の診断には死亡現場の状況および法医学的な証拠を必要とする。 外因死の中でも窒息死と診断するためには、体位に関係なく、 ベッドの隙間や柵に挟み込まれるなどで頭部が拘束状態となり回避出来なくなっている、 などの直接死因を説明しうる睡眠時の物理的状況が必要であり、 通常使用している寝具で単にうつぶせという所見だけでは診断されない。 また、虐待や殺人などによる意図的な窒息死は乳幼児突然死症候群(SIDS)との 鑑別が困難な場合があり、慎重に診断する必要がある。 * 諸外国では生後7日以上(あるいは1ヵ月以上)で生後9ヵ月未満の乳幼児突然死症候群(SIDS)と それ以外の年齢の乳幼児突然死症候群(SIDS)とを区別して考える場合があるが、 これはより典型的な乳幼児突然死症候群(SIDS)を集積して原因を解明することを目的とした 研究推進のための分類である。 付記: 少数意見として、高津光洋分担研究者より、乳幼児突然死症候群(SIDS)は疾患とすべきではない、 及び本ガイドラインに窒息死と診断するための説明を記載すべきではない旨の意見があった。 その提言は文部科学研究費研究成果報告書に記載されている。 今後の課題と提言: 乳幼児突然死症候群(SIDS)を正しく診断するための取り組みについて 1) 全国の小児医療の臨床現場で、乳幼児突然死症候群(SIDS)に関する知識の啓発と普及を行い、 死因が明らかでない予期せぬ突然死を解剖検査なくして乳幼児突然死症候群(SIDS)と診断せず、 警察への届出と解剖の必要性を家族に十分説明するように周知徹底する必要がある (小児救急医療を含む小児医療の臨床現場への適切なパンフレットの作成、配布が望ましい) 2) 警察・警察医の死亡状況調査のためのプロトコール作成と普及および死体検案講習会の開催など、 死体検案体制を早急に整える必要がある。 3) 乳幼児突然死症候群(SIDS)と窒息などの外因死との鑑別は、 解剖所見のみでは困難な場合があり、病歴、生前の健康状態、 状況証拠などを総合的に検討する必要があるところから、 小児科医、病理医、法医の間で諸検査、解剖精度、死因診断などについて 共通の認識のもとに行われることが望まれる。 4) 乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク因子に関しては、 時代とともに変わることが報告されており、我が国においても解剖された 乳幼児突然死症候群(SIDS)を対象として、死亡児の病歴、発育、 生前の健康状態、などに関して聞き取り調査を継続的に実施することでリスク因子を把握し 広くキャンペーンを展開し発症を軽減する必要がある。 5) 乳幼児突然死症候群(SIDS)の病態解明および予防法の確立に関する研究を進め、 呼吸循環系の異常を早期に発見するためのモニタリングシステムの 開発などを検討する必要がある。 乳幼児突然死症候群(SIDS)に関する研究、その他の取り組みについて: 6) 乳幼児突然死症候群(SIDS)の病態を究明するために、 運営の倫理基準を定めて症例登録システムあるいは解剖で得られた 臓器を集積するtissue bankシステムの構築を検討する必要がある。 7) 死亡診断書(死体検案書)の分類上「12.不詳」と記載された場合、 およびその後正確な死因が確定した場合には、 不備照会ならびに記載事項訂正手続きが迅速に遂行される必要がある。 8) 乳幼児突然死症候群(SIDS)で児を失った家族、 特に母親に対する精神的なサポートの重要性の社会的認知を高め、 そのサポートを行っていくことが重要である。 9) 乳幼児突然死症候群(SIDS)の大半は、 最も社会的に脆弱な生後6ヵ月未満の乳児であり、 またその発症に保育環境が関与するところから、適切な保育環境が重要であること、 母親や父親、その家族の存在が大きいこと、などを一般社会に啓発していくことが重要である。 平成17年4月18日 |
|
左の文章は、
|
|
|
||
具体的にどうするべきか
|
||